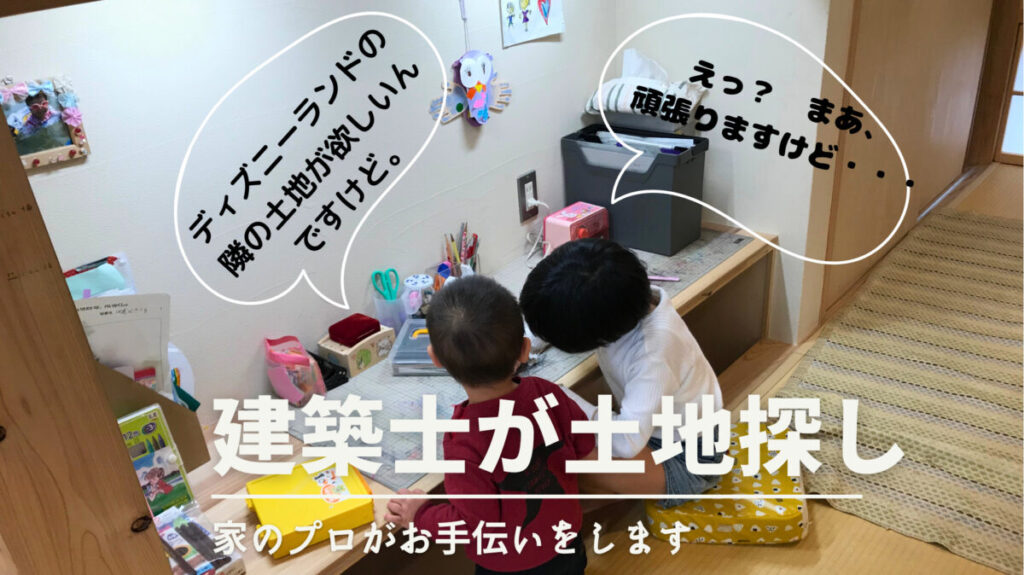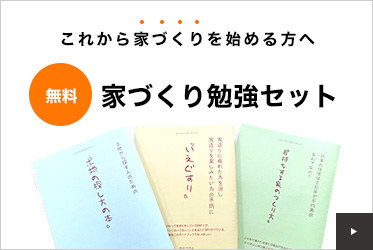家にかかる金額を下げる方法
2025年08月24日
今日のブログは面白くないですよ。文書だらけ 数値だらけでつまんないです。
ただ、これを知っていただければ10年後 20年後ホッとしながら生活ができると信じています。
私の最近の活動
- 中古再販住宅に取り組んでいる不動産会社を見つけて実態調査と物件調査。
- 古い住宅の耐震補強を構造の先生方に聞いて回る。
- 地盤と地震の関係について研究する。
- 狭小住宅は得意だけど、タマゴグミよりも狭小な家を作っている工務店さんを視察する。どうも土地の幅が5メートルを切る土地で家を建てている工務店があるらしい。
すべては、土地を含んだ家の価格を1000万円下げるための行動です。

世帯年収700万円のご家庭は家にいくらまでかけられるの?
AIに聞いてみました。
家族構成や子供の条件など入れて最初返ってきた答えが
「世帯年収500万円の方は借入可能額2400万円まあ頭金を合わせて3000万円
世帯年収700万円の方は借入可能額4200万円 だからう~ん5000万円弱ですかね」
と寝ぼけた回答をしてきました。
そこで何度となく会話を重ねて帰ってきた答えが下記のものです。どちらかというと私が言わせたというところもありますか・・・
【AIが私との会話の末出してきた安全な住宅ローンの金額回答です】
私たちは、お客様に以下の3つの鉄則を基に資金計画をお考えいただくことをお勧めしています。
鉄則1:借入は「世帯年収」ではなく「主たる生計者の年収」で考える
- 根拠:離婚・離職リスクへの備え
- 近年、3組に1組が離婚すると言われています。住宅ローンを夫婦の収入合算で組んだ場合、離婚によって返済が困難になるケースは少なくありません。また、どちらかが病気や介護、あるいはキャリアチェンジで離職する可能性もゼロではありません。
- そのため、主たる生計者(例えばご主人の年収500万円)だけで無理なく返済できる範囲で借入額を決めることが、最も堅実なリスクヘッジになります。配偶者の収入は、あくまで「家計のゆとり」や「繰り上げ返済の原資」と考えるのが賢明です。
- 具体的な計算例(主たる生計者の年収500万円の場合)
- 年収倍率を安全な5倍とすると、借入額の上限は 2,500万円 となります。
鉄則2:返済負担率は「手取り年収の20%以内」を目指す
- 根拠:物価高・教育費増に対応する「家計のゆとり」の確保
- 一般的に返済負担率は「額面年収の25%以内」と言われますが、これはあくまで金融機関が融資する際の基準です。物価高が続けば、食費や光熱費はさらに上昇します。お子様の成長に伴い、塾や習い事などの教育費も増えていきます。
- そこで、税金や社会保険料を引いた**「手取り年収」の20%以内**に年間の返済額を収めることをお勧めします。この「5%の差」が、将来の不測の事態に対応できる「家計のゆとり」を生み出します。
- 具体的な計算例(主たる生計者の年収500万円、手取り400万円の場合)
- 手取り年収400万円 × 20% = 年間返済額 80万円
- 月々の返済額に換算すると、約6.7万円 となります。
鉄則3:金利上昇を想定した「ストレステスト」を行う(これいい考えです)
- 根拠:金利変動リスクへの備え
- 現在の変動金利は歴史的な低水準ですが、35年という長期の返済期間中には金利が上昇する局面も十分に考えられます。
- 金融機関は融資の審査の際、実際の適用金利ではなく「審査金利(ストレステラス金利)」と呼ばれる3~4%程度の高い金利で返済能力をチェックしています。私たちもこれに倣い、将来金利が3%程度まで上昇しても、家計が破綻しないかをシミュレーションしておくべきです。
- 具体的なシミュレーション(借入額3,000万円、35年返済の場合)
- 金利1.0% の場合:月々返済額 約8.5万円
- 金利3.0% の場合:月々返済額 約11.5万円
- 月々の返済額が約3万円も増加します。この上昇分を吸収できるかを、現在の家計状況と照らし合わせて冷静に判断する必要があります。
結論:安心して返済できる借入額の目安
上記の3つの鉄則を踏まえ、世帯年収700万円(主たる生計者500万円、配偶者200万円と仮定)のご家庭が、様々なリスクを考慮した上で安心して返済していける住宅ローンの金額は、
ズバリ、2,500万円~3,000万円
がひとつの現実的で安全なラインだと考えます。
この金額であれば、
- 主たる生計者(年収500万円)の年収倍率5~6倍の範囲内
- 手取り年収(約400万円)に対する返済負担率も20%台前半
- 将来の金利上昇にも対応しやすい
という条件を満たしやすくなります。
「思ったより少ない」と感じられるかもしれません。しかし、家は建てて終わりではなく、そこで家族が幸せに暮らし続けることがゴールです。住宅ローンに追われる生活ではなく、旅行や趣味、お子様との時間も大切にできる、ゆとりのある暮らしを守ることこそが、私たち工務店がお客様に提案すべき本当の価値だと信じています。
まずはこの安全なラインを基準に、土地探しや建物のプランを一緒に考えさせていただき、その上で、どうしても譲れないご要望があれば、ご夫婦の将来設計を丁寧にお伺いしながら、どこまでリスクを取れるかを一緒に検討していく、という進め方が理想的ではないでしょうか。
もう一度 家は土地と建物 諸経費や付帯工事も含めて3000万円ちょっと を考えなくちゃ
タマゴグミの現状事例を話しましょう。
条件:土地 岐阜市内で50坪 建物26坪程度(4人家族) 断熱等級6 耐震等級3 外構込み
価格は
土地が1000万円プラス諸経費100万円程度 建物本体2700万円程度 外構他200万円程度 太陽光等造エネ・仕上げ等のオプション250万円 諸経費(銀行手数料等すべて込み)250万円程度 合計4500万円
これでもタマゴグミは安いほうと言われています。
新築は資産になる
残念ながら日本ではなりません。
いくら高性能の住宅を建てようともです。(多少は価格差はできます)それは、諸外国のように家にローンをつけるのではなく、借りる人の価値にローンをつける日本の仕組みがそうさせているのです。(詳しく知りたい方はこちら) マンション価格や都会の住宅価格が高騰していますが、あれはあくまでも場所の価格です。
新築すると断熱性能が良くなるからエネルギーコスト削減で十分元が引ける。 そんなものも嘘です。
断熱性能を上げる一番の効果は家全体が快適になることと、健康寿命を延ばすためです。お金を浮かすのはほんの少しの効果です。
新築の価値を高めるにはどうしたらいいのか
新築の時 将来少しでも家の価値を高めるのであれば、重要なのが地域で人気のあるエリアに建てことです。これが一番効果的!これ以上の効果がある方法はありません。
耐震等級は許容応力度計算での3(特に基礎を重視) 断熱等級は6前後 変わった設備はつけない。 家の形は単純に将来的に間取り変更をしやすいように構造区画を重視した設計。屋根は軒をつけて単純な形に、雨もりリスクと外壁に雨をあまり当てない
そんな家を地域で人気のある土地に建てる。
それでも家は資産にはならないのです。
【本題】 価格を1000万円落とすには
まず考えつくのは建てる家をコンパクトにすることです。
土地は立地が良い場所で変形土地や小さな土地を選択する。土地幅が狭かったり、周りの土地区画より20%程度小さいだけで単価がガクッと落ちることはいくらでもあります。
ただし、いくら安いとっても利便性の悪い土地はお勧めできません。
ただ現実的には、この方法で落とせる金額は大体300~700万円程度でしょう。
価格を大きく落とすには中古再生住宅が良いと思います。
中古住宅を買い取り、リノベーションする方法です。
金額的なイメージとしては
中古住宅 500~800万円 フルリノベーション1400~2000万円 諸経費250万円程度 合計2200~3100万円といったところです。
下の写真はタマゴグミがリノベーションしてみた物件です。写真の物件で、改装費用・中古物件・諸経費込みの総額で約2900万円程度です。

中古再生住宅のデメリット(予算2000万円以下の改修の場合)
- 耐震等級3まで改良できる物件は少ないです。
理由は基礎と地盤です。
上部構造はどんな形でも補強はできます。ただし、壁や床を強くしすぎると地震の時に基礎が持たなくなり基礎の破壊や基礎だけ残して建物が横に吹っ飛んでしまう可能性があります。
Point
中古再生住宅の耐震改修の場合は構造計算は必須です。壁を強くすればよいという安易な耐震改修はしないのが鉄則です。
- 断熱等級は最上等級7を取るのは難しいです。
無理ではないですが、そこまでコストをかけて改修するのるのであれば新築を狙ったほうが良いでしょう。
狙うのは断熱等級5(HEAT20 G1)レベルです。
とはいってもきっと納得できる断熱改修は可能と考えています。
中古再生住宅と住んでいる家のリノベーションとは違います。中古再生住宅は価格と性能のバランスをとることが重要です。お金が許されるのであれば新築のほうが良いに決まっています。
住んでいる家をリノベーションする場合は「愛着と思い」を重視しますので、予算よりも性能を重視することも少なからずありますが、中古再生住宅には不要と私は考えます。
中古再生住宅のポイント
最大ポイントは どんな物件を買い取るかです。
新しい物件だからよいというわけではありません。床がブカブカしているから悪いというわけではありません。
場所は地域で人気がある場所か、価格は妥当か、改修する価値がある物件か、 改修はしやすいか 間取り変更はやりやすいか 以上の5つのポイントが重要となってきます。
ですので、中古再生住宅をお考えの場合は建築する業者(設計事務所もしくは工務店)を先に決めることが成功の秘訣といえます。
上記5つのポイントをあなたに判断してくださいと言っても難しい話です。残念ながら不動産にも建築にも強いプロに頼むしかないと私は思います。
すべては資金計画から
まずは新築を考えてみましょう。それのほうがきっと満足度は高い。
だけど、資金的に難しい場合は中古再生住宅はお勧めです。
大切なのは、今の年収や『みんながそうしているから』という理由で焦って大きなローンを組むことではありません。
まずはご自身の家庭にとっての『安全な資金計画』を知ることです。
タマゴグミでは、お客様の10年後、20年後の笑顔を第一に考えた資金計画の無料相談も行っています。まずはお気軽にご自身の『安全ライン』を知ることから始めてみませんか?」
この記事を書いたのは
株式会社タマゴグミ 一級建築士 井手 徹です。