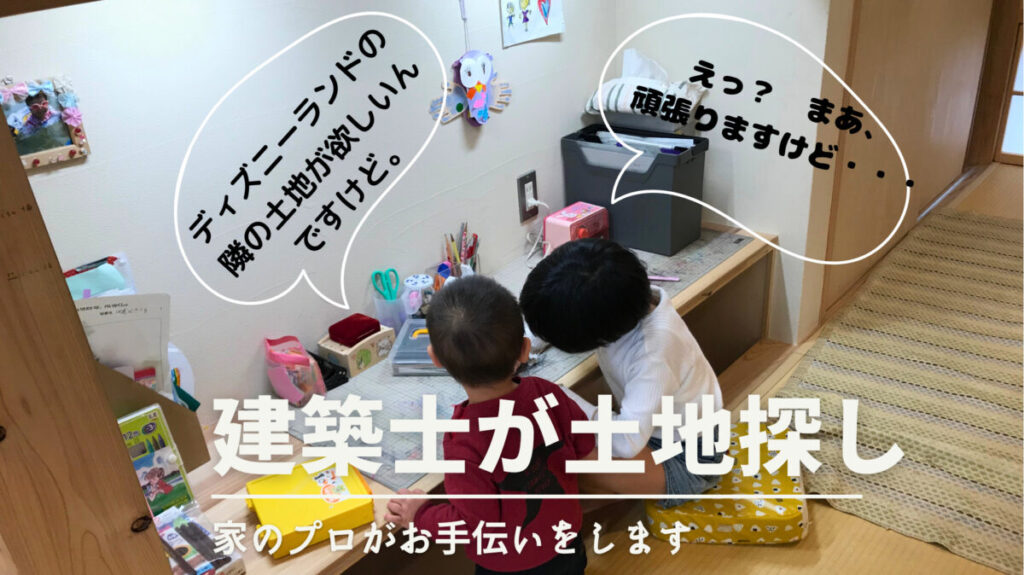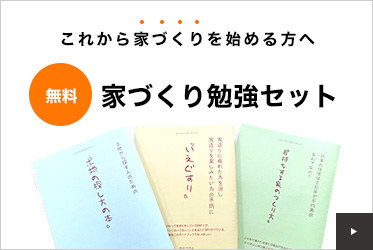羽島市で3年越しのリノベーション。この家が、私に「新築を1000万円下げる」家づくりを教えてくれた。
新築に限りなく追いつきたい
羽島市で3年かけてリノベーションをした物件です。
この家を作らせていただいたこと そしてご購入頂いたお客さまは私の家づくりに大きな影響を与えてくださいました。
その結果、2025年から「新築を1000万円下げる新しい新築の形。」という考えで再生住宅での家づくりに取り組みだしました。
その話は最後にします。
まずは完成した姿を見てください。
外壁は年月とともに周りに溶け込んでいく杉板を

外の壁は以前のトタンをすべてめくり、内部にダイライトという火に強い面材を貼ったうえで、杉板張りにしています。
玄関周りは、屋久島杉を使っています。年間それなりの屋久島杉を使っていますので、案外手ごろな値段で使用できます。
ちなみに、軒の天井も屋久島杉ですが、これは節だらけで捨てられそうになっていたものをいただいて使っています。つまり材料費は実質タダです。
2階の杉板は、倉知製材さんの倉庫に大量にあった板を格安で譲ってもらいました。どれだけ安いかというと、玄関周りに貼った屋久島杉の5分の1の価格です。 もともと内装材に使用する予定なものですので、表面もつるつるしていて、非常に良い材料です。 この辺りは、製材屋さんとつながっているという、弊社の強みを生かしています。

倉知製材さんで見つけた杉板。さすが構造部材を製材している会社で、材料もきちっと乾燥しており、良い材料です。
屋根は軽いほうがいいけど、いぶし瓦は残したかった。
 のし瓦が乗っている状態。瓦谷さんに言わせると、1トンほどの重さがあるようです。 |
 のし瓦をおろした状態。ちょっと寂しくなりましたが、地震には強くなりました。 |
瓦は以前のものそのまま使用しています。
なんたっていぶし瓦ですので、この街並みにはあった材料です。また、解体時に雨漏れも確認されず十分使用に耐えると思い使用しました。
ただ、屋根の**飾り瓦(のし瓦)**はおろしました。のし瓦は重量があるのので地震時に不利になるからです。
開口部は性能重視


開口部は暑さ寒さに大きな影響を与える部位です。 玄関は海外製の断熱ドアを、窓などの開口部はすべて樹脂サッシのペアガラスを採用しました。
周りが開けた場所に建つ家ですので、景色はどこから取り入れてもよい場所です。 安価に性能を上げるために景色を消す(景色の良い窓を潰して壁にする)という妥協はせず、高性能な窓を採用しました。
居間は「おおっ」と思える仕上げを

何も入っていない状態ですので、ちょっと寂しい写真になっていますが、結構いい仕上げとしています。
床は北海道の無垢のタモです。とはいってもこれもB品。正規の品にならなかったものを格安で譲ってもらい使用しています。
壁と天井は由布珪藻土を使用しました。また、天井の一部は胴縁の目透かし貼り。
キッチンは、ご購入いただいたお客様にお選びいただき設置しました。

夜の様子ですが、家具が少し入った状況です。
以前この場所は2間続きの和室でした。
大きい家の余った部屋は
実はこのお宅は延べ坪40坪程度ある大きな家なのです。
そこでこんな部屋を作りました。

床を一段落として、土間のような部屋にしました。
正面左に見えるのは、玄関から続く小さなにじり口。外に続くサッシは掃き出しで全て開くタイプです。
住まわれる方が、どんな風に使ってもOKな部屋です。
バイクを持ち込んでニヤニヤしながら眺めるもよし、
自宅でお仕事をする方は作業場兼接客の場にしてもよし
外に近い第二の居間にするもよし
今回は、どうも楽器演奏の場になったようです。ピアノが備え付けられています。
2階は機能的に
2階には3部屋の個室をつくりました。
以前は4部屋だったものを、一つの大きな部屋と8畳間を2つにしました。
本当はもっと開放的にするつもりでしたが、構造的にこれが限界でした。

主寝室となる16帖の部屋。ベットを置いてさらにはちょっとした居場所も作れます。
価格がすごく上がってしまった新築では夢のような部屋です。

階段を上がったホールは、ちょっと不思議な空間にしたいと思い変わった照明を設置しました。
大規模リノベーションにはつきもの、余ったスペース
間取りまで大きく変えるリノベーションにつきものなのが、余ってしまったスペース。
そのスペースをいかにも「はじめっからこんな感じにしたかったんだぞ」風に仕上げてしまうのが建築士の力。(って、裏話をしてしまっていいのか?)
それでできたスペースがこちら

玄関から続く手洗い。
はじめは物置にしようかと思ったのですが、大きな家だったので、大きなウォークインクローゼットもあるし、各部屋にも十分な物置もあります。
だったらちょっとした手洗いを作ってしまおうと思いつくりました。
この家の性能は
断熱等級は5。 耐震性能は壁量は耐震等級3以上の量 梁や柱・一部基礎の強さは許容応力度計算の耐震等級2相当です。
断熱等級は上部構造だけなので、数値化できますが、耐震等級は、地盤や一部基礎、水平構面の問題で耐震等級2と、正確には言い切れません。
設計者判断という場所があるのが事実です。
なお、ホームページにはビフォーの話は一切しません。あくまでも新しい形の新築物件としてみてほしいからです。
この物件の改装物語は一番下の動画で付けました。よろしければご覧ください。
第2部 再生住宅という選択

ここからは興味がある方だけ読んでください。
書いてある内容は、再生住宅の価格について、再生住宅を選ぶこと についてです。
再生住宅は一体いくらなの?
今回の住宅の情報です。
【改装前の仕様】
- 場所:岐阜県羽島市 (調整区域・既存宅地)
- 土地の大きさ:54坪 この地域では一般的な大きさより少し小さい
- 建物の大きさ:41.5坪 かなり大きな物件です
- 以前の間取り:1階に8畳の和室が3部屋。DK 水回り 2階に8畳の部屋4部屋
【改装後の仕様】
- 住所・土地・建物の大きさは変わりません。
- 耐震性能:壁量計算による耐震等級3 梁と一部基礎は許容応力度計算によるチェック
- 断熱等級:等級5
新築の場合いくらかかるのか
羽島市の土地相場は安いです。このあたりで坪単価10万円程度です。
- 土地価格は540万円
- 建物の大きさ41坪、そして結構いい仕様 たぶん価格は3500万円程度(タマゴグミ価格)
- それに、外構費用や上下水道のつなぎなどで250万円程度
- 諸経費が土地購入の経費を入れて250万円程度
- 合計4540万円程度
頭金を540万円 あと4000万円をローンとすると 月々の支払いが128000円程度(2025年10月フラット35)
このローンを支払っていく理想の年収は770万円程度です。
この物件(中古再生住宅)の価格は
実際に取引した価格は出せませんので、タマゴグミとして理想的な価格を書きます。
- この物件の仕入れ値:500万円
- そしてこの物件のタマゴグミとして請求したいリノベーション費用(解体や外構も含む):2300万円
- 合計:2800万円
- 諸経費:200万円程度
- 合計3000万円です。
頭金を500万円として、ローンは2500万円。月々の支払いが8万円程度(2025年10月フラット35)
このローンを払っていく理想の年収は480万円となります。
新築と比べて1500万円落とせるのです。
改装に2300万円? 高すぎるんじゃない?
外構工事に200万円 解体工事に100万円 本体に約2000万円かかっています。
2010年代なら2000万円あれば新築が建ちました。弊社も1700万円台の家もつくっていました。
今は不可能です。最低2500万円程度からです。40坪の家になると3000万円は軽く超す金額です。
中古再生住宅は何と比較するかが重要
耐震補強もそこそこ、断熱改修もそこそこで内部水回りや壁紙を変えただけの中古住宅との比較となると、はるかに価格が高い商品となります。
タマゴグミがつくる中古再生住宅は限りなく新築に近づけることをコンセプトとしています。
よって、新築と比べて頂きたいと思ってつくっています。
今回ご購入されたお客様もまさにそうで、はじめは新築を考えていらっしゃいました。
タマゴグミと一緒に資金計画したところ、予想以上に価格が高いことに気づかれました。
そこで、今回の再生住宅を提案しました。
実際の建物を見ていただき、その後価格の提示をさせて頂いたところ、即決していただきました。
資金計画上 決して新築が買えないわけはありませんでしたが、余裕のある生活という選択を選ばれました。
中古再生住宅の弱いところ
利点は、価格が一番です。それでは問題点は何でしょうか?今回の物件について書いてみます。
1.地盤の問題
地盤調査が義務化されたのは2000年からです。その前の物件は地盤調査ははほぼしていませんし、地盤改良もやっていない場合が多いです。
ただし地盤は10年もすれば安定してしまいますし、それまでに不動沈下してなければ大丈夫です。
地震については、その土地によって違いますので、それはプロの目利きに任せることになります。
2.基礎の問題
基礎に鉄筋が義務化されたのは1981年からです。それまでは無筋(鉄筋がない状態)の基礎がほとんどでした。また、たとえ鉄筋が入っていたとしても許容応力度計算にかけてみるとほとんどの物件がNGとなります。
今回の物件は、構造計算をかけて必要なところに基礎を作り直しています。南北の通りに対しては、基礎の内側にさらに基礎を作り、その上に土台を敷くといった2重壁にしています。
3.水平構面の問題
聞きなれない言葉ですね。簡単に言い換えると「床の強さのの問題」です。
壁の補強や梁の補強は骨組みにしてしまえば さほど難しいものではありません。
床も、すべてめくってやり直せば可能ですが、結構大変で費用が掛かります。
4.断熱等級6以上
断熱等級を6以上にするには結構手間がかかります。サッシはもちろんのこと、付加断熱も当然となってきます。
ここまで希望されるのであれば、新築をお勧めしたいと思います。
これらのことが再生住宅の問題点と考えています。
再生住宅の価値向上のために
良い家にまじめに作り替えることはもちろんですが、それ以上のことも考えていきます。
今回の物件を施工、そして弊社で取引をさせて頂いていろいろ課題と気づきがありました。
お引渡し半年後に伺ったとき、お庭に小さな耕運機がおいてありました。
「どうしたんですか?」と聞くと「Oさんから畑を無償で借りたんです。畑仕事を始めました。」とのこと。Oさんは、この家の以前の持ち主で近くに住んでいらっしゃいます。
お客様が引っ越しされたときから何かとお気遣い頂いています。
その時ハッと気づきました。
中古住宅を買うということは、その家の人付き合いや環境、文化を買うことになるんだということです。
不動産取引では、その土地大きさ法規的なこと、近くに何があるか、建物の大きさなどは情報として出ていますが、その家の持ち主のことは一つも載っていません。というか載せれないのでしょうね。
しかし、買われる方は結果その家の歴史や人間関係をも買うことになります。
そのあたりも、情報として出す必要があるのではないかと考えています。
先日ダメもとで、東京の大きな不動産ポータルサイトの会社に行ってきました。「新しい形の中古住宅検索サイトを作ってくれませんか?」と
興味を持っていただき、少しづつ動きが出てきました。
中古住宅も野菜の生産者のように顔が見える取引ができるようになればと思います。それが取引全体の2%でもいいので。
音声でもどうぞ。後半はブログにないことを解説しています。
この記事を書いたのは
株式会社タマゴグミ 一級建築士 井手 徹です。